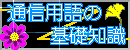

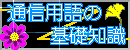 |
 |
| 等級 |
| 辞書:科学用語の基礎知識 天文学編 (UAST) |
| 読み:とうきゅう |
| 外語:magnitude |
| 品詞:名詞 |
天体の見かけの明るさを表わす尺度。数値が大きいほど暗く、小さいほど明るい。絶対等級と区別するため「見かけの等級」と表現することもある。
|
|
| 概要 |
地球から観測される星の見かけの明るさ(観測される輝度)を対数スケールで表現したもの。
天体から地球に届いた見の光の強さは、光は距離での減衰に加え、途中の星間ガスなどでの減衰もあり、実際の星の明るさ(光度および輝度)には相関がない。あくまでも地球からの観測輝度の表現である。
天体が本当に放射している光の明るさは、これとは別の概念である光度で表現される。
| 特徴 |
| 由来 |
星の見かけの明るさは千差万別であり、このため古くから明るさに尺度を付けることが模索された。
大昔には星の明るさを計測する手段がないため、紀元前2世紀、ギリシャの天文学者ヒッパルコスは、夜空で一番明るい星を1等星、目で見える一番暗い星を6等星とし、その間を2等星・3等星・4等星・5等星と分類する方法を発案した。
これを、2世紀の天文学者プトレマイオス(トレミー)が「アルマゲスト」においてこの方式を採用したことで広まったとされている。
時は流れ1830(天保元)年、イギリスのジョン・ハーシェルは1等星の明るさは6等星の明るさの約100倍であることを発見した。つまり6等星が100個集まれば1等星の明るさに見える。つまり1等級間の明るさの違いは1001/5倍、つまり約2.5(2.5118864315)倍と求められる。
このため1等星は2等星の約2.5倍明るく、2等星は3等星の約2.5倍明るく、3等星は4等星の約2.5倍明るいということになる。
| ポグソン |
1856(安政3)年にはイギリスの天文学者ポグソンが6等星の明るさの平均を求め、それを基準に100倍明るい星を1等星、途中は2.5倍ごとに区切った現在の等級を作った。
また従来の法則を拡張し、1等星より明るい星、6等星より暗い星も定義された。
つまり6等星の約1/2.5の明るさを7等星として、以下8等星、9等星、と続けることで、肉眼では暗くて見えない恒星にも等級を与えることが可能となった。
逆に1等星の約2.5倍の明るさの星を0等星、そのまた約2.5倍明るい星を-1等星(マイナス1等)とし、-2等星、-3等星と続けることで、より明るい星にも等級を与えることができるようになったほか、等級も小数による表示を可能としてより厳密な表現も可能となった。
| 等級の原点 |
こと座α星ベガが0等級であることから、これを基準にしていると説明する例が多々あるが、これは正しくない。ベガが0等級であるのは単なる偶然である。
「天文月報 1997年1月」に記載された市川隆著の記事「標準測光システム」![]() によれば、元々は、1884(明治17)年にエドワード・ピッカリングが北極星(こぐま座α星)を2.0等と定義したことに始まる。その後、こぐま座λ星を6.5等と定義し直し、北極星野の暗い星を多数観測した。そして、1922(大正11)年にローマで開催された第1回IAU(国際天文学連合)総会で、北極星野の96個の星を国際式等級の原点にする、と定めた、される。
によれば、元々は、1884(明治17)年にエドワード・ピッカリングが北極星(こぐま座α星)を2.0等と定義したことに始まる。その後、こぐま座λ星を6.5等と定義し直し、北極星野の暗い星を多数観測した。そして、1922(大正11)年にローマで開催された第1回IAU(国際天文学連合)総会で、北極星野の96個の星を国際式等級の原点にする、と定めた、される。
つまり、明るさが変動したり、超新星爆発で突然なくなってしまうかもしれない特定の恒星の明るさを基準にしているわけではない。
| 表現方法 |
一般に1等星と呼ばれる星は1.5等星より明るい星となり、つぎのようなルールに従う。
| 主要な天体の等級 |
現在全天に、1等星は21、2等星は67、3等星は190、4等星は710、5等星は2000、6等星は5600あるとされている。
ちなみに太陽も月も等級で表現可能で、太陽は-26.8等、満月は-12.7等である。太陽と満月の等級差は14.1等あり、明るさの差は約2.514.3とすると約40万倍もあることが分かる。
| リンク |
| 通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Ver 7.04a (27-May-2022) Search System : Copyright © Mirai corporation Dictionary : Copyright © WDIC Creators club |